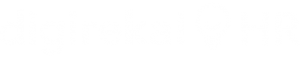圧迫面接という言葉が蔓延り、その賛否が問われています。しかしながら、
・圧迫面接とは何か正しく理解できていない
・自分が圧迫面接をしてしまっていないかわかっていない
・圧迫面接をしないようにしたい
という方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、本記事では、「圧迫面接の具体例」「圧迫面接を行う理由」「圧迫面接しないための方法」などを解説します。
採用課題を解決するなら、300社以上の支援実績を誇る
uloqo(旧PrHR)の面接代行サービス
このような課題を抱えていませんか?
・採用活動におけるリソース不足にお悩みを抱えている
・面接や書類選考で、改善や採用広報等に手が回らない
・どうしたら採用活動がうまくいくのかよく分からない
uloqo面接代行サービスは、結果にコミットし、採用目標達成に向けて、
あらゆる打ち手を考案・実行します。
採用戦略設計・採用広報企画・スカウト媒体・人材紹介会社・SNS等、
あらゆる採用手法の活用、候補者対応まで、採用に必要な機能を
豊富なノウハウと実績を活かし、高い品質でご提供します。
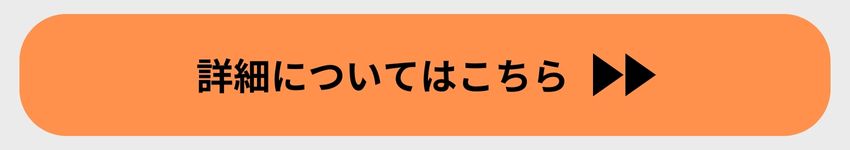
圧迫面接とは
圧迫面接とは、面接官の高圧的な態度や発言により、求職者が返答し難い面接のことです。もっともよくある例が、面接中に面接官が話を聞かない、全く興味がない様子を示す、といった態度によって求職者を圧迫するものです。
また近年では面接官が深く鋭い質問を投げかけたことによって、「圧迫面接をされた」と捉える学生も多いです。意図せず圧迫面接と捉えられないようにするためにも、圧迫面接について詳しく知っていくことが必要です。
圧迫面接の具体例5選
圧迫面接が具体的にどのような発言や態度であるかイメージがついていない方もいらっしゃるのではないかと思います。そこで、圧迫面接の具体例をいくつか紹介いたします。
選考とは無関係の質問をする
1点目は選考とは無関係の質問をすることです。家庭環境や本籍についての質問をすることは本人の能力とは無関係の要素によって、選考を行っているという点で不適切な質問となります。
厚生労働省の「公正な採用選考の基本」の中では、応募者の能力により選考を行うことが推奨されているため、本人の能力と関係のない質問をすることは圧迫面接となる可能性があるのです。
応募者の発言を全否定する
2点目は応募者の発言を全否定することです。ここでいう全否定とは、応募者の発言が妥当であったか否かに関わらず、頭ごなしに否定することを指しています。
具体的には以下のような発言が圧迫面接として扱われる可能性があります。
・あなたの志望動機には共感できないです
・あなたの考え方は弊社とあっていないです
・あなたの言っていることは妥当ではないです。
などが挙げられます。
どの発言も、応募者の発言を全否定するものであり、圧迫面接であると判断される可能性があります。
応募者自身のことを否定する
3点目は応募者自身のことを否定することです。応募者自身の否定とは、応募者の発言を否定するのではなく、応募者の人格や能力そのものを否定することを示しています。
具体的には以下のような発言が圧迫面接として扱われる可能性があります。
・あなたはこの職種には向いていないですよ
・あなたの性格だと入社してから苦労しますよ
・あなたの能力だと活躍するのは難しいですよ
などが挙げられます。
これらは、応募者自身の人格や能力を否定した発言であり、圧迫面接にあたります。
応募者のことを無視/興味のない態度を取る
4点目は応募者のことを無視/興味のなさそうな態度を取ることです。具体的には、以下のような態度が挙げられます。
・パソコンや携帯電話を触っている
・あくびや頬杖をついている
これらは、面接官が応募者を無視しているもしくは、興味のない態度であると判断されるため、圧迫面接となります。
高圧的な態度を取る
5点目は高圧的な態度を取ることです。高圧的な態度とは、具体的には、以下のようなものが挙げられます。
・怒鳴る
・怒った口調で話す
・首をかしげる
・不機嫌な表情をする
これらの態度は、どれも面接官が応募者を見下している態度であり、高圧的な態度といえます。
圧迫面接を行う理由4選
圧迫面接を行う企業は何のために行っているのか、よくわかっていない方もいらっしゃるかと思います。そこで、圧迫面接を行う理由を4つ紹介いたします。
応募者の本音を引き出すため
1点目の理由は、応募者の本音を引き出すためです。採用面接では、真面目で優秀な人は往々にして、事前準備をしっかりと行ってきます。そのため、表向きの綺麗に形作られたスクリプトを用意している志願者も多いと考えられます。
その場合、面接に合格するために用意した原稿と実際の応募者の考えとにギャップがある可能性があるため、面接官は応募者が
・本当に自社で働きたいと思っているのか?
・仕事に対する熱意は高いのか?
など本音を引き出すために圧迫面接を行っています。
ストレス耐性があるか確認するため
2点目の理由は、ストレス耐性があるかどうか確認するためです。ストレス耐性があるかどうか確認する会社は以下のような特徴があります。
・業務量が多い/残業が多い
・顧客からのクレームが多く精神的な強さが求められる
いずれも一般的にストレスが大きくかかる業務や環境だといえるため、このような労働環境にある企業では、入社後のミスマッチを防ぐためにも圧迫面接を行っています。
思考力を確認するため
3点目の理由は、思考力を確認するためです。高い思考力が業務内で求められる企業の場合、面接官の厳しい深堀や鋭い質問に対して、筋の良い解答を出せるかどうかを見極める場合もあります。
応募者は往々にして事前準備として、スクリプトを用意しているため、面接で頻出の質問を行うだけでは、思考力を測ることが難しいです。そのため、応募者が事前に予期できない深堀の質問を繰り返す場合があります。
柔軟性があるか確認するため
4点目の理由は、柔軟性があるか確認するためです。入社後に想定外の問題が起きて、それに柔軟に対応しなければならない場合は多くあります。そのため、企業は想定外のことに柔軟に対応できるかどうかを面接で見極めようとしています。
その1つの手段として、圧迫面接を選択する企業があるのです。想定外の質問や要求を行うことで求職者の対応力を判断します。具体的には、
・日本にある電柱の数を考えてください
・特技を披露してください
などといった質問/要求をすることがあります。
圧迫面接によって起きる採用における不利益
圧迫面接を行ってしまうことによって、どのような不利益があるのか気になる方はいらっしゃるかと思います。そこで、圧迫面接によっておきる採用における不利益を3つ紹介します。
企業イメージが悪くなる
企業の人材採用者が最も気を付けなくてはならないのが、企業イメージや評判を育成し守り続けるということです。近年圧迫面接は多くの求職者に嫌われる傾向にあります。つまり圧迫面接を求職者に施すと、圧迫面接の「企業晒し」をされる場合があります。
「企業晒し」とは、圧迫面接を施した企業をSNSにて共有し、さらに多くの求職者が知ることができるように晒す、ということです。採用活動の面接で企業ブランドを下落させる事は出来るだけ避けた方が良いのではないでしょうか。
また圧迫面接に限らず、面接で不採用となってしまった求職者は、不合格となった企業に対してマイナスなイメージを、持ち続けるということも良くあるケースです。企業にマイナスな印象を持っているままでは、サービスや商品を購入しないということだけでなく、SNSでのネガティブキャンペーンをされる可能性もあります。自社のブランドを守るためにも、採用活動には細心の注意を払う必要があります。
内定を出しても辞退される可能性がある
圧迫面接を行う2つ目のデメリットに、内定を出したとしても辞退される可能性がある、ということが挙げられます。圧迫面接を行っている企業は、マイナスなイメージを持たれることが良くあります。そのため企業に就職したとしても、職場環境が良くないのではないかという不安から内定辞退を申し出る人も多いです。
採用担当者の多大なコストをかけて、選出した内定者が辞退してしまうことは、非常に効率が悪いです。できるだけ内定者の辞退を防ぐような工夫が必要になってくるのではないでしょうか。
圧迫面接中に帰りだす求職者も
圧迫面接は求職者にとって大きなストレスです。そのため多くの求職者は我慢をし、必死に面接を受け続ける方が多いです。ですが中には、圧迫面接を未だに導入しているような会社には就職したくないという思いから、面接中に帰り始める求職者もいます。
面接中に帰られてしまうような状況を作り出してしまうことは、企業にとっても求職者にとっても良い状況ではないため、避ける事が必要ではないでしょうか。
圧迫面接は違法なのか?
厚生労働省ホームページの「採用選考のための基本的な考え方」にも「採用選考は応募者の基本的人権を守ることを基本とする」とあることからも、度を超えた圧迫面接が褒められたものではないことはわかるでしょう。では、法で圧迫面接は法律で禁止されているのでしょうか?
参考)公正な採用選考の基本 厚生労働省
実は現在のところ圧迫面接を直接取り締まる法律はありませんが、度がすぎると刑事罰に問われてしまうこともあります。そのリスクと内容について解説します。
名誉毀損罪
名誉毀損罪は刑法第230条によれば、公然と事実を摘示し人の名誉を傷つける行為を指します。
簡潔に言えば、複数の人が聞くことができるような形で事実を示すことにより、その人の社会的評価を下げた場合に問われる罪です。
例えば、複数の面接官が立ち会う中で、「前の会社のお荷物だった」といった発言があれば、名誉毀損罪が成立する可能性があります。この際、発言が真実であるかどうかは重要ではなく、そのような事実を示すことによって名誉を傷つけたとされれば、罪に問われることがあります。名誉毀損罪が成立すると刑罰として拘留や科料が科せられることがあります。
侮辱罪
侮辱罪は刑法第231条によれば、具体的な事実を示さずに公然と他人を侮辱する行為を指します。侮辱行為が不特定多数の人に聞こえるような形で行われ、その結果、被害者の社会的評価が損なわれる場合、侮辱罪に該当する可能性があります。
例えば、面接会場の外にまで聞こえる大声で、「お前は馬鹿なのか!」「使えないやつめ!」などと罵ってしまった場合、侮辱罪が成立する可能性が考えられます。侮辱罪が成立すると刑罰として拘留や科料が科せられることがあります。
圧迫面接をしないようにするには?
圧迫面接をしてしまっているか不安であったり、圧迫面接を行いたくないという方もいらっしゃるかと思います。そこで、圧迫面接を行わないための方法を3点紹介します。
・圧迫面接とは何か十分に理解する
・アイスブレイクで応募者の緊張を和らげる
・言動や態度に注意する
圧迫面接とは何か十分に理解する
1点目は、圧迫面接とは何か十分に理解することです。圧迫面接というワードは曖昧な表現であるため、人によって圧迫面接とは何か?に対する認識が異なる場合があります。
面接官が圧迫面接でないと判断したとしても、求職者が圧迫面接であると判断すれば、それは圧迫面接となってしまうのです。そのため、求職者と面接官の間での認識の齟齬を少しでも減らすために、一般的な圧迫面接の認識を十分に理解しておくべきでしょう。
どこからが圧迫面接であるかを理解することができれば、自分が圧迫面接をしているかどうかを判断することができるようになり、結果として面接スタイルを改善できます。
アイスブレイクで応募者の緊張を和らげる
2点目は、アイスブレイクで応募者の緊張を和らげることです。圧迫面接の要素の1つとして、「面接官が高圧的な態度であること」も挙げられます。面接官が自分の態度は高圧的ではないだろうと認識していたとしても、求職者から高圧的であると思われてしまった場合、その面接は圧迫面接となってしまいます。
つまり、求職者がどのように感じるのかが圧迫面接かどうかの判断に重要だといえます。求職者が過度に緊張している場合、面接官のちょっとした一言が求職者にとっては、圧迫的であると認識されるかもしれません。そのため、アイスブレイクで応募者の緊張を和らげることで、圧迫的な印象を軽減できると考えられます。
言動や態度に注意する
3点目は、言動や態度に注意することです。圧迫面接かどうかは主に面接官の言動や態度が原因となっています。
例えば、
・高圧的な態度
・応募者自身のことを否定する
・応募者の発言を全否定する
・応募者のことを無視する
などが圧迫面接の特徴として挙げられます。圧迫面接では、主にこれらの言動や態度が原因となり、求職者に圧迫的であると判断されてしまうため、自身の言動や態度を振り返ることが圧迫面接をしないようにするために重要になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。本記事では、
・圧迫面接とは何か正しく理解できていない
・自分が圧迫面接をしてしまっていないかわかっていない
・圧迫面接をしないようにしたい
という方に向けて、「圧迫面接の具体例」「圧迫面接を行う理由」「圧迫面接しないための方法」などを解説しました。参考にしていただきますと幸いです。
PrHRの採用代行サービスについてはこちら
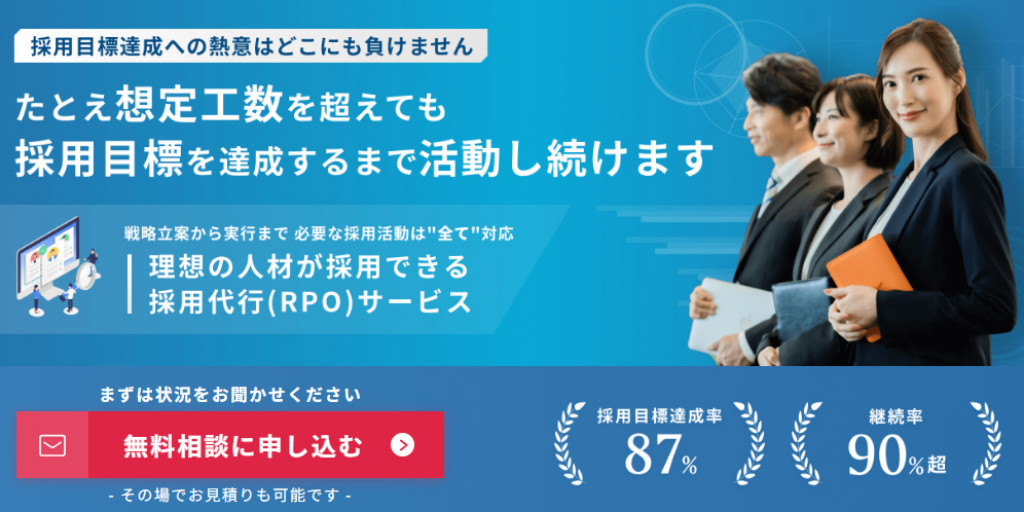
「普通の運用代行」ではない、
プロフェッショナルリクルーターによるRPOサービスです。
①月額20万円~からご予算と課題に応じてカスタマイズ型でサービス提供が可能。支援後は追加費用の発生一切なし。
②累計50社取引クライアント様の契約継続率は驚異の90%超。
③あらゆる採用媒体活用実績を活かしたプランニング、実行により、採用目標達成率は87%超。
④上流工程の企画から、下流工程の実業務まで一気通貫で支援。もちろん採用広報もベーシックプランから提供可能です。
⑤独自の業界リサーチで、業界専門用語や市場におけるクライアントのポジションについて、徹底的にインプットを行います。
⑥エンジニア・データサイエンティスト・デジタルマーケター等、専門職種についてはテクノロジー領域専門のコンサルタントが担当します。





サービス徹底比較!料金、特徴をご紹介!.jpg)